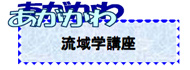|
|
|
イトヨ属は北半球の海に面したところに棲む、しかしその南限は北緯35度以北に限られる。日本においては、遡河型(降海型と同じ)で山口県(日本海側)利根川(太平洋側)となる。淡水型(陸封型と同じ)は、福井県大野市を南限に、北海道まで広がる。しかし、その多くは海に近いところの淡水に棲む海よりおよそ100kmも離れたところに生息を続ける淡水型のイトヨは、ここ会津と栃木県那須・大田原ぐらいのものである。(レッドリスト記載は陸封型のみ) 
淡水型は今ではとても貴重で食すことは出来ないが、遡河型はスーパーで春季に売られているときもある。20数尾1パックで300円くらいである。手に入ったなら良く見て欲しい。 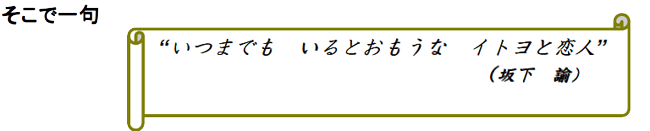
|