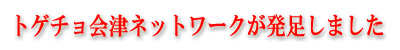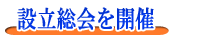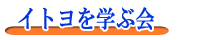|
|
| 【国】 | 国土交通省北陸地方整備局阿賀川河川事務所 |
| 【福島県】 |
○会津地方振興局 ○南会津地方振興局 ○会津若松建設事務所 ○喜多方建設事務所 ○南会津建設事務所 |
| 【市町村】 |
○会津坂下町 ○喜多方市 ○会津若松市 ○下郷町 ○南会津町 ○会津美里町 ○湯川村 ○猪苗代町 |
| 【市民団体】 |
○会津イトヨ研究会 ○喜多方市高郷町自然を守る会 ○南会津町川島地区 ○阿賀川・川の達人の会 ○NPO法人会津阿賀川流域ネットワーク |
| 【漁協】 |
○会津非出資漁業協同組合 ○阿賀川非出資漁業協同組合 ○南会東部非出資漁業協同組合 |
| 【個人】 |
○樋幸四郎(会津大学短期大学部名誉教授・阿賀川環境アドバイザー) ○成田宏一(会津生物同好会・阿賀川環境アドバイザー) |
| 【事務局】 |
○国土交通省北陸地方整備局阿賀川河川事務所 ○NPO法人会津阿賀川流域ネットワーク |
総会では今後、会を運営するにあたり、会長および8名の世話人を選出しました。選出された方々は次のとおりです。
| 会 長 | 二瓶 庄栄【喜多方市高郷町自然を守る会】 |
 二瓶会長 |
|---|---|---|
| 世話人 | 鈴木 一弘【会津非出資漁業協同組合】 | |
| 〃 | 会津若松市 | |
| 〃 | 二瓶 重和【阿賀川・川の達人の会】 | |
| 〃 | 二瓶 豊久【喜多方市高郷町自然を守る会】 | |
| 〃 | 福島県会津地方振興局 | |
| 〃 | 渡部 芳加【南会津町川島地区】 | |
| 〃 | 国土交通省北陸地方整備局阿賀川河川事務所 | |
| 〃 | 坂下 諭【NPO法人会津阿賀川流域ネットワーク】 |
また、会則に基づき、顧問に山中實氏【会津イトヨ研究会】、事務局長に高橋利雄氏【NPO法人会津阿賀川流域ネットワーク】が、二瓶会長よりそれぞれ任命されました。


設立総会の様子
総会終了後、下郷町及び南会津町のイトヨ生息地の現地見学会を行いました。また、「イトヨ勉強会」として南会津町の役場庁舎をお借りし、顧問で会津イトヨ研究会代表の山中實先生を講師に、イトヨの生態等についてお話いただきました。
【下郷町生息地】
現地の状況等について下郷町役場の玉川武之さん、南会東部非出資漁業協同組合の永峯武男さんから説明をいただきました。ありがとうございました。
- この豊富な水はその多くが伏流水である。
- イトヨだけでなく、貴重なミクリ、バイカモなどの植物も多く生育している。
- 水温は通年ほぼ一定のようだ。
- 環境としての変化はあまりない。
- 地元の人にも、ここにイトヨが生息していることは、あまり知られていない。
- 現在の生息個体数は昔の1/10程度だと思う。その原因は盗られたと思う。
- この場所を他に知られたくない。たぶん、盗られてしまう。

【南会津町生息地】
続いて見学会は南会津町に移動しました。現地は、荒海川(阿賀川)の旧河道でヤナギやアカマツ林の中にあるとても景観のよいところでした。ここでは、南会津町役場の鈴木忠男さん、南会津町川島地区の渡部芳加さんと室井藤夫さん、顧問の山中實先生よりいろいろな説明をいただきました。

- イトヨの生息地としては世界でも最高の高さ(標高600m)に生息するイトヨではなかろうか。
- 水中の植物も周辺の植物もイトヨの生息には必要である。
- 産卵は春3月頃より始まると思う。
- 出水時でも水は濁らない。伏流水でまかなわれている。
- 保全は、過去に水位が下がり、小さな湧水箇所にのみイトヨは生きていた。その時からイトヨの保護がはじまった。
- 保全活動としては大きな手は加えてない。地域のみんなで話し合い、監視している。
- ここでは中学校の総合学習でも取り上げられている。
- 他にもイトヨの生息箇所はかつては多くあったが、今では激減してしまった。

現地で採捕されたイトヨ
地元の方々には、早くから観察会のためにいろいろと準備をしていただき、非常に良い観察ができました。ありがとうございました。
【山中實先生(顧問)による勉強会】
イトヨの分布・生態などに関してのとてもわかりやすいお話しでした。

- トゲウオ科には、イバラトミヨなどいくつかの種類があり、正しくイトヨを区分することが重要である。特に公表する場合は注意する必要がある。
- オスに赤い婚姻色が現れ、粘り気のある液体を出して水底に巣をつくる。巣の中には、2つのレールみたいなものがある。ジグザグダンスを繰り返した後、オスが巣に案内して、急ブレーキを掛けることにより、メスのお腹に刺激を与える。必ずオスが横倒しになって巣の場所を示して、メスが入る。その時、オスが刺激しないとメスは卵を産めない。巣はなかなか見つけられない。
- 10日間ほどで稚魚となる。今年産卵しなかった個体は、来春の3月に通常の個体より早く産卵する。
- 繁殖期に赤いものを水中に入れるとオスがなわばりを守るために攻撃してくる。
- 田島のイトヨは、世界でも最も標高の高い所にいる陸封型イトヨである。猪苗代湖に居るイトヨは、昔からいるという説と最近確認されたという説がある。
- トゲは普段は寝ているが、餌をとる時やなわばりを守る時はトゲを立てる。
- イトヨを飼育するためには、60cm以上の水槽で水底に砂を敷く。水温はクーラーで低く一定温度にし、巣作りできる水草を入れておく。なわばりがあるので、境界上に水草を植えてお互いが見えないようにすれば、巣が造られやすい。
- トゲは普段は寝ているが、餌をとる時やなわばりを守る時はトゲを立てる。
- 体の大きさにもよるが、150〜250の卵を産卵する。体の割には卵は大きい。