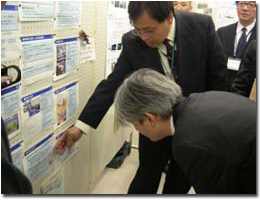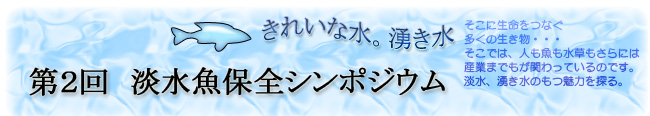 「湧水保全フォーラムinゆざ:ざわめく自然をめぐって」概要報告
去る11月17・18日に山形県遊佐町にて「第2回淡水魚保全シンポジウム」が開催されました。 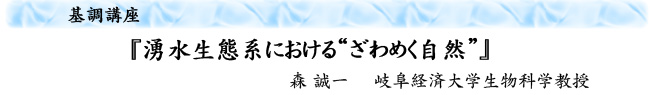 -日本=川国論-日本は山国である。この山国観を別の角度から見れば川の多さを意味する。 つまり我が国は「川のクニ」といえる。 川のクニは川の多さだけを意味するものではない。 川は平地をつくり、人を集め人を生活の場ともした。 川のクニは表層水だけをいうのではない。 伏流水も湧き水も陸水であり、日本の典型性を表すひとつである。 つまり、我が国における水環境の典型性は豊富な水資源に支えられた、「史、文化、そして多様な生物相であった。 しかし、これらは近代化に伴い変容した。 そこで、この状況を展開するには、地域が地域に思い入れをもつ「郷土力」の育成が肝要である。 -自然のざわめき:生き物の多様性-川は生活や意識の中からも距離を広げている。 自然からの様々な声、ざわめきも距離を広げている。 しかし、自然もざわめきをもたない自然が増えている。 また、自然のざわめきを感じない知覚も増えている。 人は今、ざわめく自然と接する努力もしなければ、原風景である、流域環境も消えてしまう。 私たちは個々の胸に体感して、ザワザワする自然のざわめきを自らが取り戻し、伝承すべき時がきている。 
(報告:NPO法人阿賀川河川流域ネットワーク 坂下 諭) |
||
 湧水環境に棲む淡水魚類の多様性
湧水環境に棲む淡水魚類の多様性